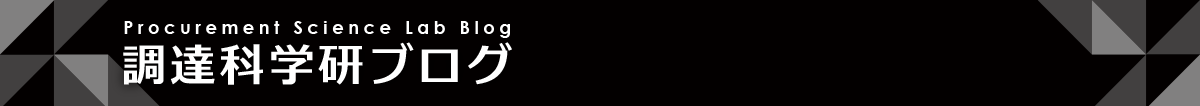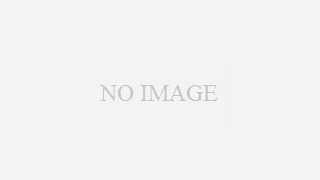 ブログ
ブログ 中国の統治の歴史~習近平はどこへ向かうのか~
秦の始皇帝が中国全土を統一したのは紀元前221年である。中華統一を果たした始皇帝は度量衡・文字の統一、郡県制の実施など様々な改革を行った。また、匈奴などの北方騎馬民族への備えとして、それまでそれぞれの国が独自に作っていた城壁を繋げて整備し「万里の長城」に結実させた。思想的には焚書坑儒を断行し抵抗勢力の芽を徹底的に摘む政策を取った。阿房宮という壮大な宮殿の建築も行い、農民は過酷な労働に苦しみ、さらに極度の圧政まで加えられた。そのことで全国各地の不満を高めてしまい、のちの反乱を生むことになる。 統一から11年後の紀元前210年に始皇帝は死去したが、主を無くした秦では全国に反乱の火の手が上がり、秦は紀元前206年に滅亡する。のちに前漢初代皇帝に就くかの有名な劉邦に降伏した秦は実はたった15年の治世で終わりを告げてしまったのである。 秦は周から王朝を奪取して成立したが、周、とくに前半の西周は儒教において理想的な時代とされている。周の政治制度は、周王が一族や功臣、地方の有力な土豪を諸侯と任じ、一定の土地と人民の支配権を与え、統治した封建制である。周王と諸侯、諸侯とその家臣である卿大夫は、擬制的な...