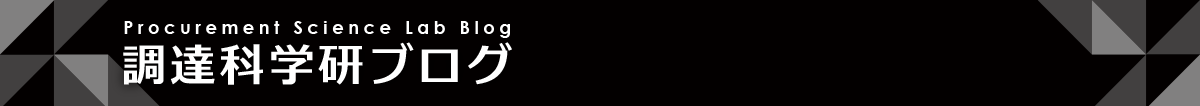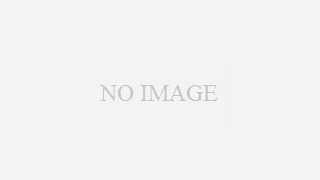 ブログ
ブログ 2023新たなる調達の視座
2022年の最大の事件は2月24日のロシアによるウクライナ侵攻でした。クリスマスや年末年始お構いなく両国の攻撃が続いています。2023年中に休戦に至るかどうかも不透明です。新型コロナウイルスによる混乱も丸三年経ち、100年前に比べて医療技術や感染予防は格段に進歩しているにも関わらず、グローバル化やWHOの指導力不足もあってか世界的パンデミックが落ち着くには3~4年は掛かるのだという改めての再認識がなされました。最近の中国のゼロコロナ対策の転換により、一気に世界へ広がりそうな陽性患者が新たな懸念材料となっています。 このような状況下、この三年間ほど、企業におけるサプライチェーンが脚光を浴びたことは過去ありません。調達部門に対してQCDのうち、QDは当たり前、Cの低減に注力してくれればいいという大方の認識は崩壊しました。もとより調達部門に属している方々はQDが当たり前とは思っていません。あるとすれば、高度成長期のJapan as No.1の時代を引きずってきた(引きずってこれた)企業や年代の人たちくらいなものでしょう。Cの低減では21世紀に入って中国が急速に台頭し、一世を風靡しました。中国...