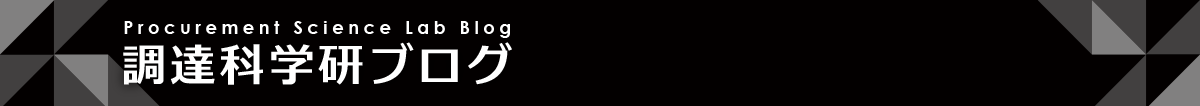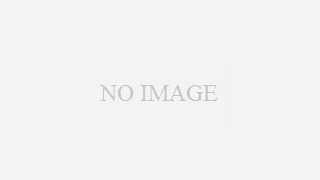 ブログ
ブログ 日本人の心に脈々と流れる武士道精神
「武士道」の解説書で有名なのは、五千円札の肖像となった新渡戸稲造の書いたものであるが、これは欧米に日本文化を正しく理解してもらおうとアメリカにおいて1900年に英語で刊行されたものであり、後に和訳されたものを日本人が読むことになったものである。ゆえに本来的に武士道精神の神髄を語ったものではない。 武士の誕生は平安時代後期と言われるが、その当時は「もののふ」などと呼ばれ、幼い頃から武芸に勤しみ、いまでも行事として残る流鏑馬などの技量が秀でた侍が称賛されていました。もう一面は「一所懸命」に代表される命を懸けて領地を守る、ゆえにそこで開墾している農民から安心料としての年貢を徴収する正当性を持っていました。そして武士の名誉として、決して避けることのできない一度きりの死を、主君のために戦場で華々しく散ることが最上の美学とされました。病床にあった前田利家は関ケ原の合戦の前に「畳の上で死ぬのは無念だ」と叫んで死んでいったと言われています。 武士道を語る上で基になるのは甲州武田家の「甲陽軍鑑」です。隆盛を誇っていた武田軍が、なぜ長篠の戦(1575)で敗れたのか、それまでの来し方を見直し、あるべき武士の...