日中のGDPが逆転したのは2010年のことである。日本が西ドイツを抜いてGDP世界第2位になったのは1968年なので、日本は42年間アメリカに次ぐ経済大国として世界にその存在感を誇っていたことになる。1968年時点の日本のGDPは1466億ドル(約51兆円)、当時中国は文化大革命の時代であり、経済数値の信頼性には疑問があるが、凡そ468億元(約1324億円)であったと推定される。日本は中国の385倍の経済規模があり、一人当たりのGDPでは(日本1億1790万人・中国7億5600万人)2474倍の差があった。
米国ニクソン大統領が中華人民共和国(中共)を電撃訪問したのは1972年。国家安全保障問題担当大統領補佐官であったキッシンジャーは前年密かに北京を訪れ、米中関係改善によるソ連の封じ込め交渉に乗り出していた。中共は1949年建国の翌月には国連に中華民国の追放を提起し、その後も何回も同様の提起を企てたが、長らく否決され続けてきた。1971年のアルバニア決議を経て中共は国連の安全保障理事会常任理事国の地位を獲得し、正式に国際舞台の主役としての地位に立つこととなった。アメリカは中華民国の国連追放までは考えていなかったが、泥沼化していたベトナム戦争を中共の影響力行使により速やかに終結させたいとの思いは強かった。しかし、その深層ではアメリカの威信を損なうことなく、自由世界の守護神として国際秩序形成において引き続き力強い役割を果たし続けるといった基本政策もあり、慎重なやり取りが米中の間で行われていた(「キッシンジャー『最高機密』会話録」毎日新聞社)。
当時、アメリカはベトナム戦争の戦費が重しとなり、経済力も低下していた。米ソ間で軍拡競争を続けていってもキリがなく、相互牽制・均衡関係・緊張緩和の方策を模索し、デタント(戦略兵器の削減による軍事バランス維持)を実現することは最重要課題であった。そのための外交政策として、中共を巻き込んだ米中ソ等距離「三角外交」の実現を目論んでいた。当時の中ソ関係も最悪と言ってもいい状況で、1969年の珍宝島(ダマンスキー島)での国境線をめぐる武力紛争以降、中共はソ連を「修正主義」と批判し、ソ連は中共を「教条主義」として非難する関係となっていた。米中お互いに対ソ牽制に向けて接近を試み、協調関係を探る国際環境ができていたことになる。
それまでアメリカを「帝国主義」と批判していた中共ではあったが、毛沢東の支持を得た周恩来が林彪を迎えて、対米接近路線の方針が出された。秋波を受けたアメリカは、米中接近に慎重なキッシンジャーより前のめりなニクソンの政治主導で前述の米中首脳初会談に至るのである。
米中交渉のその後の展開は順調とは言えず、ニクソンのウォーターゲート事件(その後、大統領はフォードが引き継ぎ、民主党のカーターに)による辞任や、中共における周批判の四人組台頭~のち失脚~周恩来・毛沢東の死去など権力闘争による混乱が続き、7年間の紆余曲折を経て、ようやく鄧小平とカーター大統領の間で米中国交正常化が合意されたのは1979年のことである。この交渉で最大の懸案となったのが、台湾問題であった。
ニクソン・キッシンジャーはなんとか中共から「友好的方法による台湾問題の解決」という正式誓約を得ようと努力を続けたが、中共から言質を取ることが出来なかった。キッシンジャーは当初の目標であった1976年の米中国交正常化に向けて、➀台湾の独立運動との関係を断つ、➁台湾からの米軍撤退(朝鮮戦争勃発時に、アメリカは台湾を共産主義から守るために、台湾海峡において米軍の軍事的存在を強化していた):具体的にはF-4ファントム機部隊と台湾に駐留する米軍9000人のうち半数を引き上げることを提案している(キッシンジャーは一方で、米国内での共和党保守派・親台湾派の反発は必至として、懐柔の難しさも吐露している)。
毛・周亡き後、最高実力者となった鄧小平は「台湾は国内問題であって、それに介入する権利は誰にもない」とアメリカ側に改めて通告し、台湾の平和的解決の保証を取り付けたいアメリカと真っ向から対立する。この間、蒋経国(蒋介石の長男)はじめ台湾側の強力なアメリカ議会への働きの結果、最終的に米中間で、台湾からの米軍の撤退の代わりに、アメリカによる台湾への武器援助は続けるという妥協が成立した。その結果として1954年にアメリカと中華民国(蒋介石政権)との間で締結された米華相互防衛条約は1980年に失効し、米台断交という結論に相成る。
一方、アメリカに遅れまじと、ニクソン訪中の7か月後に北京に飛んだ田中角栄首相は、翌年1973年には早々に日中国交正常化を決意し、椎名副総裁を日台断交を伝えるための特使として台湾へ派遣した。しかし、椎名は日台断交を言い出せず「台湾との外交を維持する」といって帰国の途についてしまった。 それでも田中角栄政権の決意は変わらず翌月、中共を「中国の唯一の合法政府」と承認し、国交を樹立した。その際、大平外相が「日華平和条約は存続の意義を失い終了した」との見解を表明。これに対し中華民国は「狼を部屋に引き入れ、敵を友と認め、中共匪団の浸透転覆活動を助長する」と日本政府を強く非難し、即日対日断交声明を発表。日台断交は米中交渉の経緯とは全く無関係に為された。
アメリカの台湾をめぐる慎重な対中交渉と比較して、日本のそれはあまりに拙速軽薄であったと感じざるを得ない。現下の台湾情勢を安倍~岸田政権が「台湾有事は日本有事」と公に発言するに至っては尚更その感を強くする。日台断交後も民間交流を従来通り維持させるため、実務的な窓口機関を相互に設置するなどの努力を通じて(超党派の日華議員懇談会など)、日台間の非公式実務交流を何とか途切れさせないように維持してきたという経緯がある。
一方、日中国交正常化を記念して1か月後には中共から2頭のジャイアントパンダ(ランラン・カンカン)が寄贈され、多くの日本国民の対中意識は「パンダ外交」によって著しく好転した。
1979年から開始された日本政府の対中ODAは3兆6000億円、国際協力銀行などを迂回した援助も合わせると累計6兆円以上に上る。1国が1国に与えた援助額としては史上最大の額である。その金の大半は中国のインフラ整備に充てられたが、中国国民には一切知らされていない。当時の6兆円という金額は現在価値換算で100兆円とも言われる。中共は浮いた国家予算を軍拡につぎ込み、過去30年間において軍事費を42倍に増やしている(日本の防衛予算の4倍)。その結果、中共は中距離弾道ミサイルを2000基保有し、人口30万人以上の日本の都市には例外なく全ての中国核ミサイルの照準が向けられて実戦配備されている。日本はロシアのウクライナ侵攻に慌てふためくNATOの危機感を、ようやく中共の台湾進攻に重ね合わせ、背中を押される形でGDP比2%への防衛費増に踏み切ったが、足元の自衛隊員の不足や弾薬は2か月しかないなど継戦能力に大きな不安を抱えている。安倍首相が主導した同盟国との連携強化(日米豪印クアッド)は最も速い防衛実戦能力増の手段であり、それだけをもってしても名宰相として歴史に名を残す価値があるであろう。
日本の対中ODAは2021年まで行われ、10年以上もGDP3位の国がGDP2位の国に資金援助を行うという狂気の媚中外交が行われてきた。それに終止符を打ったのも凶弾に倒れた安倍首相である。
中国はギネスブックにも「人類史上最大の大量殺人国家」として登録されており、中共政権による自国民殺害人数は7894万人とされる。現在でもウイグルやチベットでは虐殺と弾圧、強制労働が行われて罪もない多くの人々の生命が奪われ続けている。
1989年の天安門事件は、中共建国以来、中国共産党独裁体制の最大の危機であった。100万人規模の民主化要求デモは共産党政権を大きく揺るがした。欧米先進国は厳しい経済制裁を加え、中共は外交的にも経済的にも完全に孤立し、経済成長率も1%台に急落し、共産党政権崩壊の可能性をも指摘される状況にあった。実際、戒厳令布告の決断に関しては政治局常務委員会の意見は二つに割れ、最終的には最高実力者であった鄧小平の判断によって戒厳令布告、武力によるデモ隊弾圧に舵を切るのである。事件後、民主化運動に理解を示した趙紫陽党総書記は失脚。翌月、G7の中で日本(宇野宗佑首相)だけが「中国を国際的に孤立させるのは得策ではない」という親中声明を出し、G7サミットにおける共同制裁の声明は見送られることになった。さらに翌年、日本は天安門事件を受けて事実上凍結していた第3次円借款を何事もなかったかのように解除している。
日本民間企業の対中直接投資額は2012年がピークで134億7900万ドルにまで達したが、その後も年100億ドルペースで行われている。中国においては合弁企業が必須とされ持株比率は中共側が50%+1株と決定権を握り、技術情報開示も義務付けられ、とても対等と言える条件ではない。ようやく利益が出ても日本に送金することは許されず、合弁を解消するには、それまでの優遇税制分の返納を求められ、機械設備も没収されるといった一方的な関係である。それらの利益は中国共産党に吸い上げられ、その一部は人民解放軍の軍備増強に充てられ、先述したように日本に向けてミサイルが実戦配備されていることを知っている日本人はどれほどいるであろうか。
アメリカも欧州主要各国も中国が2001年にWTOに加盟した時(当時中国のGDPは世界6位)には、国連の安全保障常任理事国としての中国が責任をもって国際ルールに従って振舞うものと期待していたが、今から振り返れば全く甘い期待でしかなかった。核を持つ安全保障常任理事国ロシアがソ連崩壊時に核を奪い取ったウクライナに侵攻し、核の脅しをかけるなど思いもよらなかったことが、現実化した。プーチンと27回首脳会談を行った安倍首相を「結局、北方領土は還ってこなかった」と批判する向きもあるが、安倍首相は簡単に北方領土が還ってくるとは思ってはいなかった。あわよくばという気持ちはあったに違いないが、主眼は中露の連携を阻むことであった。その心はキッシンジャーのそれと大きく異なるものではない。過去との違いはロシアの国力が大きく衰え、中国の国力が格段に高まったということだけである。
最後にロシアの話に飛び火してしまったが、日本は戦後GHQによるWGIPという国家弱体化政策により従順な都合の良い国(国民)として育て上げられ、一貫して自虐史観を植え付けられきた。マッカーサーは1951年、自身の退任演説でこう述べている「日本ほど穏やかで秩序のある勤勉な国を知りません。また日本ほど将来、人類の進歩に貢献することが期待できる国もないでしょう」と。日本を二度と歯向かえないような国にすることこそが占領政策の基本にあったことは後の多くの文献によって明らかになっている。「戦後レジュームの脱却」を掲げた安倍政権が誕生するまで、中国や韓国への謝罪と忖度と援助を戦後70年以上ずっと続けてきた。自虐史観に基づいて行われた1995年の河野談話は世界に日本政府の公的な見解と受け止められ、自ら一方的な謝罪外交から抜け出せない道を作ってしまったが、ようやくその軛(くびき)から解かれようとしている。
キッシンジャーが関わった米中交渉は様々な点において、毛・周と意見を異にしたが、日ソ関係においては意見が一致していた。それは➀ソ連と日本をあまり近づけてはならない、➁日本に米国を取るか、中国を取るかの二者択一を迫らないようにしなければならない、➂日本がモスクワなどの「異なる核の傘」の下に雨宿りすることのないように気を付けなければならない、というものである。特に毛沢東は日本を再び覇権を追求してくる国家としてソ連に次ぐ脅威と見做していた。
来年1月の台湾の総統選に向けて、米中日台の関係国においては水面上でも水面下でも活発な動きが始まっている。100歳を迎えたキッシンジャーを今年7月習近平主席は北京の釣魚台国賓館に招き、米中国交正常化の立役者として厚遇した。8月に3日間にわたり台湾を訪問した麻生副総裁は、中国を念頭に「戦う覚悟を持つことが抑止力になる」と訴えた。蔡英文現総統は7月に、南米訪問の経由地としてアメリカに降り立ち、「アメリカの支持が台湾の人たちに自信を持たせている」と感謝を示し、「自信を持った台湾が地域の平和に不可欠だ。私たちの強いパートナーシップによって地域と世界がよりよくなる」と述べた。翌8月には、総裁候補である台湾民進党頼清徳副総統も同様のルートを経て、「国際社会は台湾を非常に重要視している」との考えを示し、帰国後には自民党青年局の訪問団と面会して日台の貿易関係の強化を願うとコメントしている。対する国民党総裁候補の候友宜新北市長も9月に訪米を予定している。
台湾をめぐる国際関係の力学は毛沢東・蒋介石亡き後も今日に至るまで連綿と続いている。
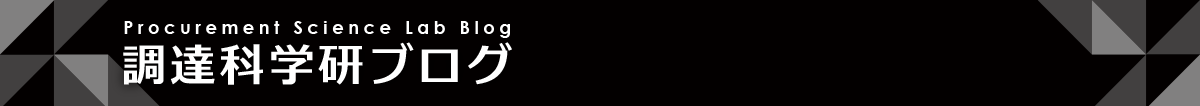

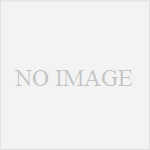
コメント